掘り抜き井戸発祥の地
- []
- ページ番号 54
概要
天明年間(1781~1789)頃まで大垣地方では、生活用水として各町の裏通りを流れる用水を利用していましたが、渇水期になると、大垣の三清水(西外側町、清水町、室町)まで汲みにゆく事になり、非常に不便でした。天明2年こんにゃく屋文七が、川端に2メートル程の穴を掘りそこに5メートルの材木を打ち込み、その後へ節を抜いた青竹を力いっぱい打ち込みました。すると、その竹の先からきれいな水が噴出してきました。これはこれはと大層喜び、「これはの井」と名付けられました。それ以来どこの家でも、自噴の井戸が掘られるようになり「井戸槽(いどぶね)」とよんでいます。

歴史
次の場所にあった大垣の三清水は藩庁から立札が建てられ、文化年間(1804-18)の初め頃より監視と保護の厳しい取締りがされ水は大切に扱われました。
- 西外側町清水口、水門川の清水橋のほとり。
- 清水町遮那院跡前駐車場近くの民家の清水。
- 当時室清水といわれた室町の清水。
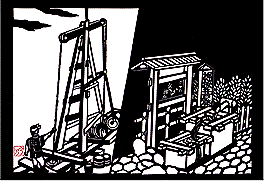
掘抜井戸発祥の地


