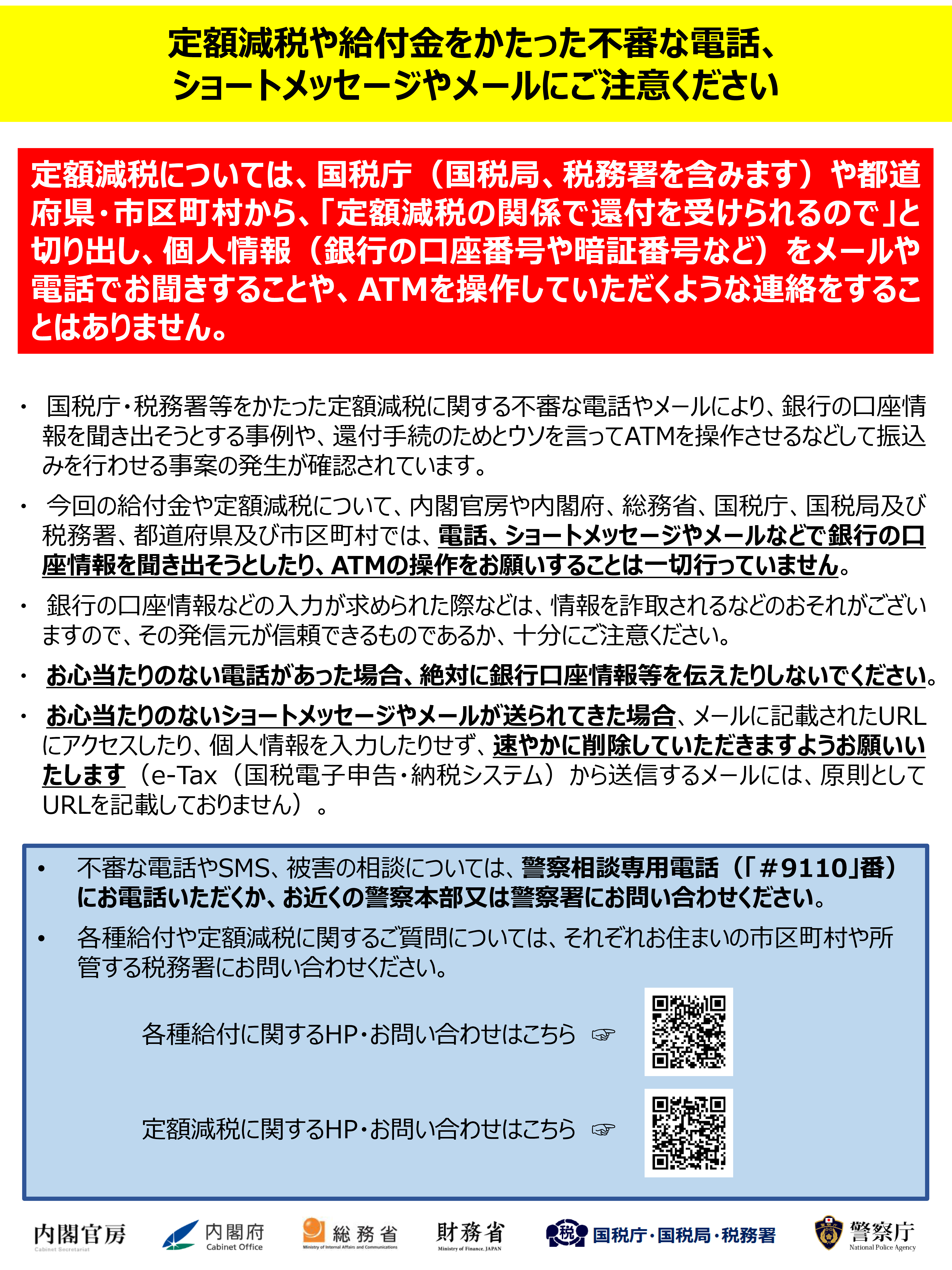市・県民税の定額減税に関するよくある質問
- []
- ページ番号 65452
市・県民税の定額減税に関するよくある質問
1 制度や対象者について
Q1-1.どのような人が定額減税の対象になりますか。
A1-1.令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下の方(給与収入のみの場合、2,000万円以下の方) で所得割が課税される方が対象です。
令和6年度の市・県民税が非課税の方や均等割、森林環境税のみ課税される方、事務所・事業所・家屋敷にかかる税が課税される方は対象にはなりません。
Q1-2.妻と子2人を扶養している場合の定額減税額はいくらですか。
A1-2. (1)本人・・・1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)・・・1人につき1万円
したがって、本人で1万円、控除対象配偶者と子2人で3万円、合計4万円が定額減税額です。
※定額減税額が所得割額を超える場合には、所得割額を上限とします。
※令和6年度(令和5年中)の市・県民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。
※扶養している方が国外居住親族(留学生など)の場合は定額減税の計算対象になりません。
Q1-3.令和6年2月に子どもが生まれましたが定額減税の加算対象となりますか。
A1-3.加算対象にはなりません。
定額減税額は令和6年度市・県民税の扶養親族数を元に加算額を算定します。そのため、令和6年2月に生まれた子どもの場合は令和6年度市・県民税の扶養親族とならないため加算対象とはなりません。
Q1-4.令和5年中は扶養親族であった父親が令和6年2月に亡くなりました。父親は定額減税の加算対象になりますか。
A1-4.令和6年度の市・県民税にかかる扶養親族の判定時期は、令和5年12月31日のため、令和6年2月に亡くなった親族は加算対象となります。
Q1-5.令和6年の途中に大垣市に転入してきました。定額減税はどうなりますか。
A1-5.令和6年度の定額減税が適用される令和6年度の市・県民税は、原則として令和6年1月1日に住所のある自治体で計算が行われます。
Q1-6.定額減税を受けるには何か申請をする必要はありますか。
A1-6.定額減税を受けるために申請をする必要はありません。
定額減税額は大垣市が保有する税情報(確定申告書、市民税・県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。
Q1-7.確定申告や年末調整で扶養の申告が漏れている親族がおり、定額減税の対象から外れています。どのような手続きが必要ですか。
A1-7.「令和6年度市民税・県民税申告書」に扶養親族を記入の上、大垣市役所 課税課 市民税グループへ郵送もしくは持参してください。
Q1-8.あとから所得の修正や扶養を変更した場合はどうなりますか。
A1-8.通常の税額変更と同様に、定額減税額が減少し所得割額が増加した場合は、追加課税となります。また、定額減税額が増加し所得割額が減少した場合には、残りの納期限において税額を変更することとなります。
Q1-9.配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除により市民税・県民税の所得割が0円となった場合は定額減税の対象となるのですか。
A1-9.定額減税の対象とはなりません。
Q1-10.令和5年中に収入がなく、令和6年度の住民税は非課税です。定額減税は適用されますか。
A1-10.定額減税は適用されません。
定額減税は令和6年度に市・県民税の所得割額が課税される方が対象です。
なお、収入が無く、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されています。
Q1-11.定額減税額を確認したいのですが。
A1-11.定額減税額は市民税・県民税・森林環境税の各種通知書において確認することができます。
※通知時期については従来から変更はありません。
(1)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月上旬頃 個人あてに送付予定)
・「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書」
・「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書(口座振替用)」
・「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 公的年金からの特別徴収(継続)税額決定通知書」
(2)給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃 お勤め先から配布予定)
「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」
Q1-12.給与所得以外にも所得があり、給与からの特別徴収の他、自分でも納付します。その場合の定額減税はどのように控除されますか。
A1-12.定額減税に係る徴収方法の優先順は法定されておらず、各市町村において、令和6年6月以降の実務上できる限り早いタイミングで減税が行われるように対応することとされています。
そのため原則として、給与特別徴収→普通徴収→年金特別徴収(年金所得があり特別徴収対象者のみ)の順で控除します。
Q1-13.定額減税額が税額から引ききれなかった場合はどうなりますか。
A1-13.定額減税額が引きれなかった場合は、調整給付が行われます。
※ 調整給付の支給対象となる方には、給付金額を記載した通知をお送りする予定です。
2 事業所の方向け
Q2-1.今回の個人住民税の定額減税で会社(特別徴収義務者)として何か個別の手続きは必要ですか。
A2-1.特別な手続きは必要ありません。
定額減税額は大垣市が保有する税情報(確定申告書、市民税・県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。従来と同様に通知された金額のとおり差し引き、納入してください。
Q2-2.今年度の特別徴収について、給与から差し引く金額が6月分が0円の方とそうでない方が混在するのはなぜですか。
A2-2.定額減税が適用される方は6月分が0円、適用されない方(合計所得金額が1,805万円超の方や均等割・森林環境税のみ課税される方など)は6月分が通常どおり発生します。
Q2-3.6,000円で7月分のみ差し引く従業員と、6,000円で6月分のみを差し引く従業員がいます。このまま差し引いてよいですか。
A2-3.差し引く金額が6,000円以下の方の場合、従来と同様に最初の納入月で1回で納めていただきます。
7月分で差し引く方は、定額減税が適用されて所得割が0円となり、均等割と森林環境税の6,000円のみとなった方になります。
一方、定額減税対象外の方は、通常どおり6月分で差し引きます。
Q2-4.特別徴収義務者において、市・県民税の定額減税額の引ききれなかった額、残額を管理する必要はありますか。
A2-4.特別徴収義務者が残額を管理する必要はありません。大垣市から通知された金額のとおり差し引いてください。
Q2-5.所得税と同様に市・県民税の定額減税についても、会社で計算する必要はありますか。
A2-5.計算する必要はありません。
特別徴収義務者用に記載の金額は、大垣市が定額減税額を計算し、定額減税が反映された金額となります。
Q2-6.退職手当に対する課税される市・県民税は定額減税の対象ですか。
A2-6.対象にはなりません。
Q2-7.定額減税に係る給与等の源泉徴収事務、年末調整等について知りたいのですが。
3 その他
Q3-1.定額減税はふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか。
A3-1.定額減税の影響はありません。
算定の基礎となる令和6年度分の市・県民税の所得割額は定額減税前の所得割額です。
Q3-2.令和7年度も定額減税は行われますか。
A3-2.一部の方が対象になります。
具体的には「令和7年度の個人市民税・県民税において扶養親族として控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する方」です。
Q3-3.所得税の定額減税について知りたいのですが。
Q3-4.税額シミュレーションシステムで定額減税額の確認はできますか。
A3-4.「税額試算結果」画面で確認できます。なお、「税額試算結果」画面に記載のとおり、算出税額枠内の税額は定額減税額を差し引く前の金額となります。税額シミュレーションシステムについてはこちら(外部リンク)(別ウインドウで開く)。