つくしっこ通信 No.101
- []
- ページ番号 66302
家族みんなで感染症を予防しよう!
例年、12月~4月頃はインフルエンザの流行期に入ります。
また、新型コロナウイルス感染症によりインフルエンザの流行が低調であったこと等の影響で、抗体の保有割合が全年齢で低下傾向となっています。そのためインフルエンザの流行が起きやすくなっています。
インフルエンザ予防対策は、他の感染症予防対策としても有効です。乳幼児や高齢者のいる家庭は特にご注意ください。
インフルエンザはどのように感染する?
インフルエンザの主な感染経路は、飛沫感染と接触感染の2つです。
(1)飛沫感染
感染者の咳やくしゃみ、会話などにより飛び散ったウイルスを鼻や口から吸い込むことで感染します。
(2)接触感染
ウイルスがついたドアノブや手すりに触れると、手にウイルスが移り、そのまま鼻、目、口等を触ることで感染します。
かからない、うつさないために
(1)手洗いをしっかりと
外出から帰ったら、まず手洗いを。アルコール消毒も効果的です。
(2)人ごみは避ける
インフルエンザが流行してきたら、できるだけ人混みや繁華街への外出を控えましょう。特に妊婦や高齢者、体調の悪い方、睡眠不足の方は注意が必要です。やむを得ず外出して人混みに入る可能性がある時は、不織布製のマスクを着用することで、飛沫感染等をある程度防ぐことができると考えられています。
(3)生活習慣を整えて抵抗力をつける
十分な休養とバランスのとれた栄養摂取を心がけましょう。
(4)室内の換気と加湿
新型コロナウイルス対策としても十分な換気が重要です。換気設備や換気扇を常時運転し、最小限の換気量を確保しましょう。
また、空気が乾燥すると感染症にかかりやすくなります。特に室内は乾燥しやすいため、加湿器などを使って適切な湿度(50~60%)を保つことも効果的です。
(5)流行前の予防接種で重症化を防ぐ
インフルエンザの予防接種は任意接種です。ワクチンの接種は感染後に発症する可能性を低くしたり、発症後の重症化を防止したりするのに有効と報告されています。
接種回数は、原則13歳未満の人は2回、13歳以上の人は1回です。
発熱などの症状がある場合は…
・まずは、かかりつけ医等の身近な医療機関に電話相談し、案内に従って受診してください。
・熱が下がってもウイルスは体内に残っているため、数日は学校や職場などに行かないようにしてください。
小学生になって「言葉」の問題で困らないために・・・赤ちゃん時代こそ大切な大人の言葉かけ
うちの子は、いつ言葉が出るようになるのかな。子どもとどうやって関わればいいのかわからない・・・
日々育児に奮闘されているご家族に悩みはつきものです。お子さんの言葉の発達のためには、大人の働きかけは欠かせません。
日々の関わりのヒントにしてくださいね。
教えていただいた先生は…NPO法人「ひまわりの花」公認心理師・言語聴覚士 中野 たみ子先生です。
「ことば」は自然には育ちません!~スマホばかりみていませんか~
一人で歩くことができる頃に、意味のあることばが出てくることが発達の目安ですが、自然に出てくるわけではありません。
◇◆ポイント◆◇
●おむつ替えやお風呂に入る時など赤ちゃん時代には“言葉のシャワー”をかけましょう。
(例えば、「おむつきれいにしようね」「すっきりしたね」など)。
●生後4か月を過ぎてくると、お子さんから声を出したり微笑みかけたりしてきます。大人も真似して発音して返したり、言葉で返したりしましょう。
赤ちゃん期は脳の神経のネットワークを作る時期!!

大人からの働きかけによって、脳のネットワークが築かれます。
◇◆ポイント◆◇
●お子さんの反応に合わせた声かけは、愛着形成につながります(例えば、おむつ替えの時に「くさいくさい変えようね」 離乳食を食べる時に「ゴックンできたね」など)。
●「いないいないばあ」の遊びで、人への意識を高めましょう。
●十分な睡眠は、お子さんの発達には欠かせません。小学校低学年でも脳の発達のために9時間は睡眠が必要といわれています。
お子さんからのサインに応じていますか?
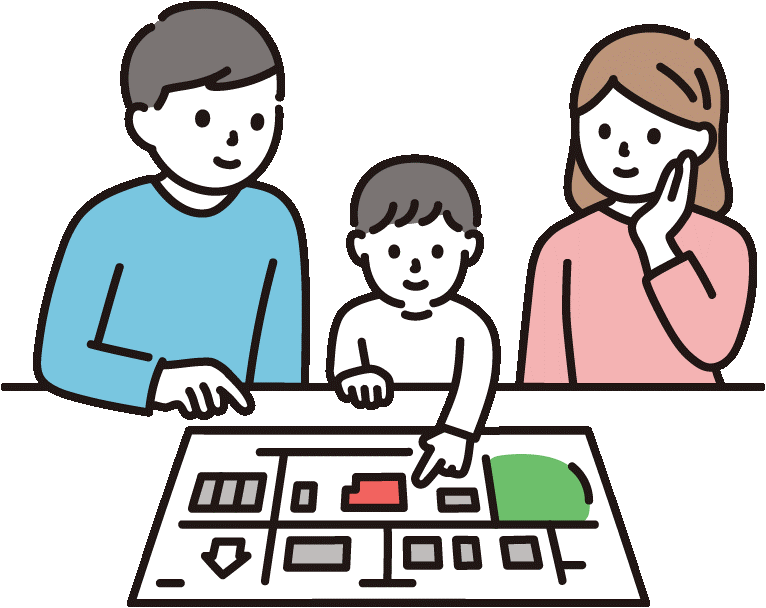
子どもからのサインは、表情・視線・発声・手ざし・指さし・動作などさまざまです。「あー、あー」と言いながら手ざしや指さしをするのは立派な「こどもの言葉」です。
◇◆ポイント◆◇
●サインに「これね」「あっち?」などの代名詞でなく、「マンマね」「お茶ね」など物の名称で返すとよいでしょう。
お子さんとの関わりの中で、ぜひ少しでも取り入れてみてください。
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

