ミニ奥の細道を歩きませんか
- []
- ページ番号 1000
ミニ奥の細道とは
松尾芭蕉が元禄2年(1689年)に、江戸深川から600里(約2,400キロメートル)を5ヶ月間にわたって巡遊し、『奥の細道』をここ大垣で結びました。
大垣市では、『奥の細道』で詠まれた句を句碑として、市内を流れる水門川沿いの「四季の路」に設置し、「ミニ奥の細道」として整備しました。
芭蕉の俳句を味わいながら、散策をお楽しみください。
◆で囲んである番号は、下の説明に対応しています。
【始】千住(東京都)

行春や鳥啼き魚の目は泪
(ゆくはるやとりなきうおのめはなみだ)
元禄2年(1689年)3月27日、芭蕉は深川から舟で隅田川を遡り、千住大橋あたりに上陸しました。そこで見送りの人々と別れるときに詠まれた句で、「矢立の初め」(旅日記の1句目)と記されています。いよいよ旅の始まりです。
【1】日光(栃木県日光市)
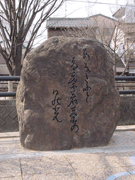
あなたふと青葉若葉の日の光
(あなとうとあおばわかばのひのひかり)
日光東照宮に参拝した芭蕉は、その神聖で荘厳な雰囲気に心打たれました。東照宮の威徳、ひいては徳川幕府に対して、素直に敬意の気持ちを表して詠んだ句です。芭蕉はその後、華厳の滝と並び称される名所・裏見の滝も見物しています。
【2】遊行柳(栃木県那須町)
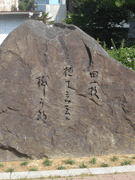
田一枚植て立去柳かな
(たいちまいうえてたちさるやなぎかな)
日光を出発した芭蕉は、黒羽に長期滞在した後、殺生石(せっしょうせき)を経て、謡曲「遊行柳(ゆぎょうやなぎ)」で知られる柳を見に行きます。ここは尊敬する西行法師が「道のべに清水流るる柳陰しばしとてこそ立ちどまりつれ」と詠んだ所でもあり、芭蕉は深い感動に包まれました。
【3】須賀川(福島県須賀川市)

世の人の見付けぬ花や軒の栗
(よのひとのみつけぬはなやのきのくり)
白河の関を越え、みちのくに入った芭蕉は、須賀川の等窮(とうきゅう)宅を訪ね、数日間滞在しました。この間に訪ねた可伸(かしん)庵で詠んだ句がこれです。芭蕉は俗世間から離れて静かに暮らす可伸を、古の西行や行基にもたとえるなど、大いに好感をもちました。
【4】笠島(宮城県名取市)

笠嶋はいづこさ月のぬかり道
(かさしまはいずこさつきのぬかりみち)
安積山(あさかやま)や文字摺石(もじずりいし)といった歌枕(和歌世界の名所)を訪れた芭蕉は、仙台伊達藩の領内に入りました。陸奥守に左遷され、この地で死んだ歌人藤原実方と、かつて実方の塚を訪れた西行の二人を思い、深い愛惜の念を込めた句です。
【5】平泉(岩手県平泉町)

夏艸や兵共が夢の跡
(なつくさやつわものどもがゆめのあと)
仙台を過ぎ、日本三景の松島はじめ多くの歌枕を訪ねた芭蕉は、さらに北上して平泉に至りました。ここはかつて奥州藤原氏が栄華を誇った地であり、悲劇の武将・源義経最期の地でもあります。奥州藤原氏の館跡にたたずみ、芭蕉は人の世のはかなさを思い泣きました。
【6】封人の家(山形県最上町)

蚤虱馬の尿する枕もと
(のみしらみうまのばりするまくらもと)
さらに北上したい気持ちを抑え、南西に向かった芭蕉でしたが、陸奥・出羽国境にある尿前(しとまえ)の関で関守に怪しまれて出国に手間取り、日が暮れたのでやむなく国境の番人の家に泊めてもらいます。そこは枕元まで馬の尿をする音が聞こえてくる家でした。「蚤」「虱」「尿」と、和歌では詠まれない題材を重ねて、句として成り立つのが俳諧の真骨頂です。
【7】尾花沢(山形県尾花沢市)

涼しさを我宿にしてねまる也
(すずしさをわがやどにしてねまるなり)
険しい山越えを果たし、尾花沢に到着した芭蕉は、豪商の俳人・清風(せいふう)を訪ねました。清風は人柄もよく、旅の辛さを知る人だったので、芭蕉はここで気持ちよく旅の疲れを癒し、人々とも交流しています。尾花沢では、みちのくで最も長い十日間滞在しています。
【8】立石寺(山形県山形市)

閑さや岩にしみ入蝉の声
(しずかさやいわにしみいるせみのこえ)
尾花沢の人々に勧められ、芭蕉は寄り道をして立石寺に参詣しました。深閑と静まりかえった山寺での、あまりにも有名な一句です。ただし、この句は初め「山寺や石にしみつく蝉の声」だったものを、芭蕉が何度も推敲してこの形になったと言われています。
【9】本合海(山形県新庄市)
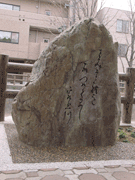
さみだれをあつめて早し最上川
(さみだれをあつめてはやしもがみがわ)
立石寺から戻った芭蕉は、最上川を舟で下ります。このころの最上川は五月雨で水かさが増え、日本三大急流の名に恥じぬ勢いでした。ちなみに、この句も初め「さみだれをあつめて涼し最上川」だったのを、実際に激しい川下りを体験して変えたのです。
【10】出羽三山(山形県羽黒町)

有難や雪をかほらす南谷
(ありがたやゆきをかおらすみなみだに)
俳人・露丸(ろがん)の紹介状を携えて羽黒山に登った芭蕉は、別当代(べっとうだい)の会覚阿闍利(えがくあじゃり)に面会し、南谷の別院で慈愛のこもったもてなしを受けました。清浄な気がみなぎるのを感じて詠んだ句です。その後芭蕉は出羽三山の残るニ山、月山・湯殿山にも登っています。
【11】酒田(山形県酒田市)
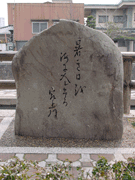
暑き日を海に入レたる最上川
(あつきひをうみにいれたるもがみがわ)
ようやく日本海側の酒田に着いた芭蕉でしたが、季節は夏真っ盛り。出羽三山に登った疲れもあり、暑さが相当こたえた様子です。夕日がまさに日本海に沈もうとする頃のかすかな涼風がありがたく感じられるのも、昼間の厳しい暑さゆえのことだったのでしょう。
【12】越後(新潟県出雲崎町)

荒海や佐渡によこたふ天河
(あらうみやさどによこたうあまのがわ)
象潟(きさかた)から酒田へ戻った芭蕉は、日本海沿いを南下していきます。古くからの佐渡への渡航地である出雲崎で詠んだ句がこれで、黄金と流人の島・佐渡、荒波、そして夜空に横たわる天の川という三者の取り合わせに、七夕の恋のイメージがより強調される名句です。
【13】市振(新潟県糸魚川市)

一家に遊女も寝たり萩と月
(ひとつやにゆうじょもねたりはぎとつき)
北陸道最大の難所と呼ばれた親不知(おやしらず)を越えた港町・市振での、芭蕉と遊女との出会いを詠んだ、たいへん艶やかな一句です。もっともこの話は芭蕉の創作というのが定説で、芭蕉が恋をテーマにした一章を加えようとしたものと理解されています。
【14】那古(富山県射水市)

わせの香や分入右は有磯海
(わせのかやわけいるみぎはありそうみ)
市振の関所を通過し、黒部川を越え、那古(なご)の浦を経て、越中から加賀に入るときに詠んだ句と言われています。熟した早稲から漂ってくる香りを詠んだのは、ここが豊饒の地であることを示すとともに、稲の育成や田の情景の変化により、旅の時間の経過を伝えることを意図したものとも考えられます。
【15】金沢(石川県金沢市)

あかあかと日は難面も秋の風
(あかあかとひはつれなくもあきのかぜ)
加賀前田藩百万石の城下町・金沢で地元の俳人たちと交流した芭蕉は、小松へと向かいます。その道中で詠んだ句で、残暑の厳しさを強調しつつも、風は確かに秋らしさを感じると詠み、長旅の旅情を感じさせます。
【16】小松(石川県小松市)

しほらしき名や小松吹萩薄
(しおらしきなやこまつふくはぎすすき)
小松において芭蕉は、対照的な2つの句を詠んでいます。1つは小松の地名を詠んだ軽やかなこの句。そしてもう1つは、多太(ただ)神社で木曽義仲追討の平家軍に加わって討死した齋藤実盛(さねもり)の遺品を前に詠んだ鎮魂の句「むざんやな甲の下のきりぎりす」です。
【17】那谷寺(石川県小松市)

石山の石より白し秋の風
(いしやまのいしよりしろしあきのかぜ)
小松から山中温泉に向かう途中、芭蕉が那谷寺を参詣した際に、岩山の奇観を詠んだ句です。那谷寺の那は那智から、谷は谷汲からつけられた名で、全国観音札所の総納め所であることを示します。史実では山中温泉の帰りに那谷寺に行っており、『奥の細道』では順序を変えています。
【18】加賀全昌寺(石川県加賀市)

庭掃て出ばや寺に散柳
(にわはきていでばやてらにちるやなぎ)
山中温泉に8泊した芭蕉は、同行の曽良が病を得て先に伊勢長島へ向かったため、ここ山中で別れることとなります。加賀藩の支藩・大聖寺の郊外にある全昌寺に泊まったのは、先行した曽良が泊まった翌日のこと。芭蕉は曽良と別れた寂しさを改めて感じるのでした。
【19】敦賀(福井県敦賀市)

名月や北国日和定なき
(めいげつやほっこくびよりさだめなき)
越前に入り、天龍寺・永平寺の二つの寺を参詣した芭蕉は、福井で2泊した後、仲秋の名月を敦賀で眺めるために出発しました。ところが、着いた日は晴れて月が美しかったのに、仲秋の名月当日は雨。北国の変わりやすい天気を残念に思いつつも、見られなかった名月を詠むのもまた風雅のかたちです。
【20】色の浜(福井県敦賀市)

さびしさやすまに勝ちたる浜の秋
(さびしさやすまにかちたるはまのあき)
敦賀湾北西岸にある色の浜は、西行が「潮染むるますほの小貝拾ふとて色の浜とはいふにやあるらん」と詠んだ地で、芭蕉にとってはぜひとも訪れたい場所でした。舟でここに渡った芭蕉は、秋の夕暮れの寂しさを、「源氏物語」の「須磨」のシーンになぞらえつつ、「須磨」よりも勝っていると表現しました。
【結】大垣(岐阜県大垣市)
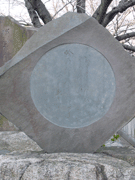
蛤のふたみに別行秋ぞ
(はまぐりのふたみにわかれゆくあきぞ)
敦賀まで迎えに来ていた路通(ろつう)とともに、芭蕉は美濃に入り、大垣に着きました。大垣には曽良をはじめ多くの門人が集まり、芭蕉の無事と旅の成功を祝います。『奥の細道』の旅の終わり。しかしそれは芭蕉にとって、新しい旅の始まりです。9月6日のことでした。

